
|
|
須藤実和
大前・アンド・アソシエーツ 経営コンサルタント
[ マーケティング ]
|
|
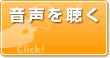
|
|
須藤実和
[インタビュー]
|
|
技術よりも「心」が問われる
2007.05.20
[ TOPBRAIN RADIO ] あのベストセラー著者に聴く!
|
|
|
理論と感性、どちらも欠いてはいけない
――女性だから書けたマーケティングの本

|
マーケティングを「科学する」
---本日のゲストはダイヤモンド社より出版されている5万部のベストセラー「実況LIVE マーケティング実践講座」の著者、須藤実和さんです
よろしくお願いします。
---大学で教鞭をとられているそうですが、どういったテーマでお話をされるんですか?
私がやってきたコンサルティングを方法論として教える「コンサルティング技法」です。本当は私自身は、コンサルティングは心でするもので技法というのには少し抵抗はあったんですが、コンサルティングの考え方を学生が社会に出たとき実際にビジネスに使えるようにお手伝いする、という感じで今講義をしています。
---大学1年生から履修可能なんですか?
最初は1年生も履修希望されていましたが、やはりかなり難しいので、今は3年生、4年生が中心になっています。
---大学で教えておられることと、ベストセラーとなった本書「マーケティング実践講座」とは、何か関連があったのですか?
そうですね。この本を書いた頃は、マーケティングというものが日本の企業ではあまり語られていないというか、科学されていなかったんです。何となく一部の人達が調査をやってアイデアを出してみて、それで実践してみたら当たったとか、当たらないとか、そういう世界だったと思うんです。それをきちっとサイエンスという形で整理したいな、と思っていました。ある意味で言うと、ビジネスマンであれば誰でもマーケティングというものを理解して、実践出来るようになってほしいと思って、この本を書いたんですね。
コンサルティング技法というのも、本当にビジネスをやっていく時に理論で分かっておくべきところはどこで、そこを整理すると何をやろうとしてもそれがベースというか基礎になる、そこのところを教えたいと思っているので、そういう意味ではオーバーラップするというか、重なりがあると思います。
---マーケティングと言うと、上位概念のような気がしますが、ちなみにマーケティングという言葉は、日本語に訳すとどういう意味なんでしょう?
確かに、日本語に直すと何なんですかね? 難しいですね。
---マーケティングという言葉はよく使われるし、ものすごく関心をよせられるものでありながら、でも実はそれが何なのか分からないという人が多いのではないかと思うんです。
今回、著書を読ませていただくと、ケーススタディなどもわかりやすく書かれていますよね。特に、マーケティングは一方的に企業の倫理でやってはいけない、ということが書いてある。
そうですね。この本を書くに当たって、世の中にマーケティングとは何かということに対して、真っ向から説明している本が如何に少ないかがわかりました。それはマーケティングだけではなくて、ビジネスで西洋から入ってきたたくさんの横文字の概念、それら一つ一つがそうなんですよね。だからそれを自分がまず理解することが大事で、わかりやすく説明出来るようになるためには自分が本当にわからないと駄目なんです。自分なりの理解の仕方であっても、自分が府に落ちてないと駄目。だから私自身も、勉強したという感じがしています。
---読んでいてとても勉強になります。企業を見る目といいますか、そのために必要なものがかなりギューッと詰まっているんですよね。ここまで言っていいの?と思う部分がかなりありました。
実はこれは全部、公表されたデータを加工して紹介しているだけなんです。もちろん、私の推察も入っていますが、それでもなるべくライブに、企業でこんなことが起きているのではないか、いうことを想像していただけるようにしました。ドラマの“踊る大捜査線”ではないですが、事件は現場で起きているんだ、という感覚にしたいなと、いろいろと工夫してみました。
企業が気づいていない強みを、どれだけ引き出せるか
---本書では、マーケティングのケースの中にiPodとかオデッセイなど、身近な消費財もよく出てきますが、それらを選ぶ基準は何かあったんですか?
それは割といい加減なんですけど、ここの会社のマーケティングはすごい、と私が感動したところを選びました。そういう意味で言うと、本当にリスペクトするなぁ、と。そのリスペクトする点を出したかった。
コンサルタントって実は、仕事的には“出来ていないところ”を指摘するところから始まる職業なんですが、私自身はそれはあまり好きじゃないんです。というのは、コンサルティングの一番の価値は、企業が気が付いていない強みを引き出すところにあると思うんですね。企業はその企業自体しか知らないわけですから、相対的な強みがわからないはずなんですよ。ただ単純に教科書的な100点満点から見て、それとの差であなたの会社は70点です、60点です、と言ってみても、それは仕方がないのかなと。「so what?」、つまり「それで?」っていう感じになってしまう。
だから私は、企業の良いところ、すごいところをフィーチャーして、それを紹介させていただきたい、というのがこだわりとしてあるんです。
---なるほど。その方が、企業側もやる気がでますよね。
そうなんじゃないかな、と思うんですよ。
---この本を書くにあたって須藤さんが一番イメージした読者は?
いろんな方に読んでいただきたいですが、特に座学が苦手な方に読んでいただきたいなと思ったんですよ。
---座学が苦手、とはどういうことですか?
要するに本を沢山読んでいて、新しいビジネス書が出たらパンと飛びついて、といった方じゃなくて、どちらかというと本なんか読んでもどうせわからないよな、なんて思っている方に、「いや、実は読んでみると意外と面白いし、自分で実践出来るような本があるんだな」と気付いてもらえればと、そういう方をイメージしました。
---なるほど。本書のようにマーケティング用語が、例を上げてきちんと説明されている本はあまり見たことがないなと感じたのですが、それを意識されていたからなんですね。
そういえば、そもそも女性でマーケティングの本を書いていらっしゃる人は少ない気がしますね。
そうかもしれないですね。マーケティングというと商品企画とか広告宣伝、広報という、一つ一つのテーマについて書かれている方はいると思いますが、全体の戦略というところから実践までの仕組み作りの全体像について取り組んでいらっしゃる方はいないかもしれないですね。
---なぜでしょう?
やはりマーケティングというものが、取っ付きやすいようで取っ付きにくいのかもしれないですね。
---説明も難しいですよね。それに一般的に女性の方が、分析だとか数字で何かを評価したり判断したりするのに、縁遠いですかもしれないですね。
それもありますね。マーケティングの難しさはまさに分析や理論といった部分と、感性の部分の両方を組み合わせなければいけないですから。よくありがちなのが、実は重厚長大な会社の極めて優秀な方々に多いんですけれども、どうせ消費財は売れるか売れないかわからないと、当たるも八卦、当たらぬも八卦という感じで、早い段階で感性に触れてしまうと言うか、感覚に触れてしまう。でもそれでは駄目なんです。やはりある程度科学するというか、計画をして、実行して、それに軌道修正をかけられるような、そういうちょっとお行儀の良いやり方が必要なんです。でもそれだけでは、心に響くような商品は出来ないし、売れない。そこのところのやんちゃする部分とのバランスを取るのが難しい。
ビジネスのヒントは街中に転がっている
---このところ景気も良くなる中で、マーケティングは改めて注目されているキーワードですが、過去と現在でマーケティングの考え方に変化はあったんでしょうか?
この本でも書かせていただいていますが、顧客との対話がより重要になってきていると感じます。少し難しい話になってしまいますが、簡単に言うと、お客様に聞かなければいけない部分が増えてきていると思うんです。
昔は物がそんなになかったし、技術も進化しているときだったので、新しいスペックのもの、新しい機能が追加されたものが出てくれば誰もが「おーっ!」と感動して、買おうとする時代でした。液晶テレビなどは、そういうところがあったと思うんです。今で言えば、プラズマテレビもそうでしょうか。
ただ現在は、そうした感動を呼べるものではなくて、お客様が「あ、これいいかも」っとちょっと思う、そういうポイントをどう突いていくかというか、どこでそうしたお客様と繋がっていくかが大事なんです。だから、顧客との対話の中で新しい価値を創造していく、それがこれからのマーケティングではないかなと思います。
---あんまり大上段に構えていては、駄目なんでしょうね。
そうですね。でもお客様に、例えば「どんな新しい飲み物が欲しいですか?」と聞くと、おそらく幾つか出てくるとは思いますが、結局それを出したからといって買うかどうかはまた違う話だったりしますよね。だから、聞き方もすごく大事なんです。もちろん大上段に構えず、でもシミュレーション力を発揮するというか、ちょっと狡猾さみたいなものも、アプローチの仕方としては大事になってくるのかな、と。
---実際にマーケティングの本で5万部ものベストセラーとなると、相当幅広い方に読まれていると思うのですが、実際に読者からの反響とか、この本を出したことで周りに何か動きなどありましたか?
ありましたよ。とても嬉しかったのは、私が通っているスポーツジムのインストラクターの人が読んでくれて、スポーツインストラクターの仕事にも関係するところがある、と言って下さったり、沖縄で有限会社を立ち上げたばかりの方が講演に来て下さって、すごく勇気が出たと言って下さったり。
技術的なところに共鳴して下さるのももちろん嬉しいですけれども、ちょっと変かもしれないが、この本を読んで「頑張ろう」と思って下さったり、「物が売れそうだな」「ビジネス上手くいきそうだな」と思って下されば、それが一番嬉しいという思いもちょっとありますね。
---ちなみにそのスポーツクラブで会われた方は、突然声をかけられたんですか?
ええ、そうなんです。表紙に写真があるので、おわかりになったみたいで。
---思いもよらない業種の方も読んで役に立つ、というのはすごいことですね。
そうですね。そうだと嬉しいです。
---本書ですごくいいなと思ったのは、巻末に索引が付いているんですよね。これは、付けようと思われた理由が何かあったんですか?
こういった本は、急いでいる時とか、悩んだ時とかにパッと手に取ってじっくり読みたくなるものだと思ったので。そういった時に索引があると、そこを取っ掛かりにしてこの本と近づいてもらえるというか、役立ててもらえるのではという思いがあって。
それから、本当にいろいろな言葉が出てきて嫌になるだろうな、と思ったので、そういう言葉を索引に全部並べてしまうことによって、逆にこれだけの言葉をマスターすればマーケティングもわかるようになりますよ、と伝える狙いもありました。
---本当に丁寧につくられた一冊だな、と感じたのはそういうところだったんですね。まだまだお聞きしたいことがあるんですけれども、最後にリスナーの皆さんにメッセージをいただけますか。ビジネスで活かせるアドバイスなどありましたらぜひお願いしたいのですが。
例えばですね、先日、マスカラを選んでいたときに、販売員の方に「マスカラってどのぐらい経つとなくなってしまいますか?」と尋ねたんです。男性の方はわからないかもしれませんが、中にどのぐらい入っているか見えないんですよ。だから、なくなっているのかなと思っても、本当に空っぽかどうかはわからない。すると販売員野方もちょっと戸惑って、考えてから「2カ月くらいです」と。
きっとこの方は、迷っただろうなと思います。要するに、短く言えば私は信じて買ってしまうでしょうし、でもあまり短すぎるとちょっと嘘臭い。でも私は、まだまだ世の中にそうやって売り方が難しいとか、お客さんの側でもまだまだわからないから何となく恐々と商品を使っていたり、商品の購入サイクルがわからなかったり、そういったものがたくさんあると思うんです。
ですから、本を書いておきながら言うのも変ですが、書を捨て町に出でよといいますか、街中にビジネスのヒントはいっぱいあるので、とにかく町に出ていろいろやってほしい。その中で「何でだろう」「どうすればもっと良くなるんだろう」ということを考えるのがビジネスの基本です。そんなに難しく考えなくていいので、自分の中ですっきりすることが一番だと思って、前向きに取り組んでいただければと思います。
---本日は「実況LIVE マーケティング実践講座」の著者、須藤実和さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
|









